
染織について
染織の作家・作品染織の説明
染織とは私たちの生活にはかかすことのできない布を、染めたり織ったりする技術のことです。現代の染織工芸は、平安時代の公家文化や安土桃山時代の武家文化、江戸時代の町人文化などによってうみだされた、伝統とおしゃれに対する美意識の結晶といえるでしょう。
制作工程
-
ステップ 1糸を作る
日本の染織で使われる糸は、基本的に絹糸・麻糸・木綿糸の3種類です。
-
ステップ 2
- 糸を織って生地をつくる
- 糸を染める
-
ステップ 3
- 生地に模様を染める
- 染めた糸を織る
白生地にいろいろな色の染料で模様を染めます。
糸目糊というのりで模様を描く友禅染や、型を使って染める型染があります。織物は、たて糸とよこ糸を織機にかけて交互に組み合わせて織り、生地を作ります。
糸の染め方や織り方によっていろいろな模様をつくることができ、どんなに複雑に見えても、たて糸とよこ糸の組み合わせによってできています。 - ステップ 4 着物や帯に仕上げて完成
技法紹介
染物(そめもの)
生地に模様を染める技法です。
友禅染(ゆうぜんぞめ)
友禅染は日本を代表する染物のひとつで、白生地にのりで模様を描いて、いろいろな色を染めていきます。一度着物の形に仕立ててから青花液という、洗うと色の残らない液で下絵を描きます。その下絵の線の上にのりを置き、色どうしが混まざるのを防ぎます。そして、模様に合わせて色を塗ります。最後に、こののりを洗い流し、細く白い線を残すのが糸目友禅です。また、この白い線が残らないように模様を染める方法を堰出友禅といいます。

型絵染(かたえぞめ)
型絵染は模様の下絵を渋紙という丈夫な和紙にはり、その上から彫って型紙を作ります。そしてできた型紙の上にくり返しのりを置き、連続した模様に合わせて色をさし、染める方法のことです。

江戸小紋(えどこもん)
江戸時代に武士が礼装用に着た裃に細かな柄が染められ発達しました。その後庶民の着物にも染められるようになりました。江戸小紋は、昔から伊勢型紙を使って染められます。
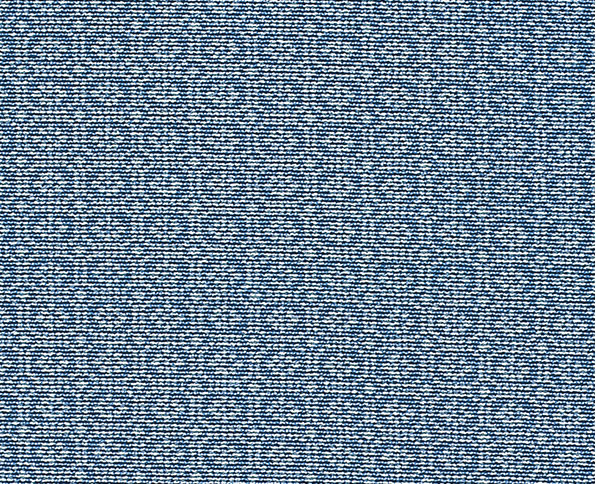
長板中形(ながいたちゅうがた)
江戸小紋は細かな模様を絹の生地に染めますが、長板中形は大きめの模様を長板(長さ約6.5メートルの板)を使い木綿の浴衣に染めます。
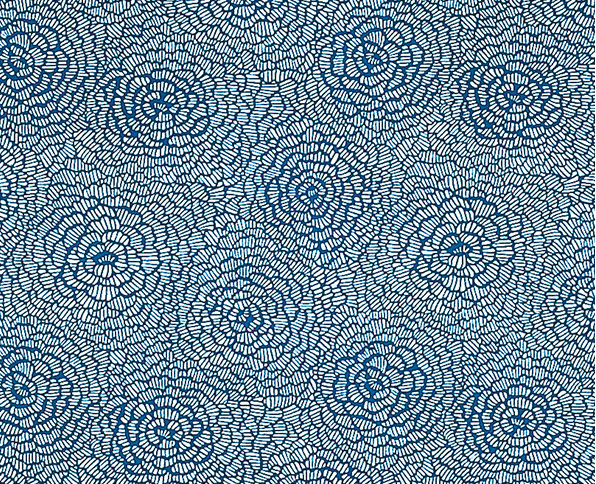
木版染(もくはんぞめ)
模様を彫った木の版に刷毛で染料を塗り、生地に当て、金づちでたたいて模様を染めつけます。

紅型 (びんがた)
紅型は、沖縄県首里市周辺で作られている染織品です。藍色だけを使用した藍染め模様の「藍型」に対して、色鮮やかな多色使いのものを「紅型」と呼んでいます。紅型の「紅」は色の総称、「型」は模様という意味で、模様の周りには隈取がされています。南国ならではの鮮やかな色合いが特徴で、模様の描き方は型紙を使用する型付けの他に、フリーハンドで模様を描く筒引きがあります。

絞り染 (しぼりぞめ)
絞り染とは、裂(きれ)を糸で括る、縫い締める、折りたたむといった方法で、染まる部分と染まらない部分をつくり模様を染める技法です。友禅染は模様を描いたり塗ったりして染めるのに対し、絞り染は染色液にひたして染めます。染まらなかった部分は白く残り、にじみやぼかしが出るのが特徴です。絞り染は日本最古の染色技法で、現在にも100種ほどの技法が伝わり、鹿の子絞り、縫い締め絞り、帽子絞りなどが有名です。

織物(おりもの)
染めた糸を織る技法です。
絣織(かすりおり)
糸のところどころを白く残して染めた絣糸を使って作られた織物のことで、染めた糸の組み合わせ方によって縞模様や格子模様、絵画のような模様を表現することができます。
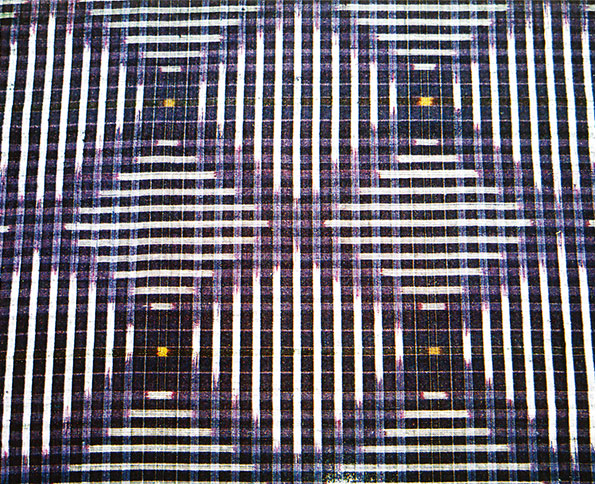
紬織(つむぎおり)
紬糸を使った絹織物です。生糸を使った絹織物にくらべて、光沢や表面のなめらかさは少なく、ざっくりした素朴な風合いになります。

越後上布(えちごじょうふ)
苧麻(別名:からむし)という多年草の茎の繊維から作られた麻糸でできた古くからある織物です。原始的な織機を使い、たて糸の張り具合を腰で調節しながら、よこ糸の柄を合わせて織ります。織られた布はお湯の中でもんでやわらかくしたり、冬の晴れた日に雪の上にさらします。色物は落ち着き、白い物はより白くなり、夏の上質な着物となります。

佐賀錦(さがにしき)
佐賀錦はよこ糸には染色した絹糸を、たてには「たて紙」と呼ばれる細く切った糸状の和紙を使います。そのたて紙を竹べらを使って模様に合わせてすくい、できたすき間によこ糸を通します。たて紙のすき間によこ糸を通すことにより、きれいにならんだ模様ができます。

組紐(くみひも)
数十本の糸を一束にして、その幾束かを交差させて組んだものを組紐といいます。組紐は、物をむすんだり、しめたりと昔からさまざまな用途に使われていました。現代では着物の帯締としていろいろな柄がつくられています。

刺繍(ししゅう)
刺繍は飛鳥時代にはおこなわれていた技法です。針と染めた糸で縫い、生地に自由な模様をつくりだします。

博多織(はかたおり)
博多織は福岡県福岡市博多地区周辺で作られている織物です。数千本にも及ぶ経糸(たていと)を打ち込むために、緯糸(よこいと)はほとんど表に出てきません。代表的な柄には、経糸によって織り出した縞柄や、仏具の独鈷(とっこ)、華皿(はなざら)をモチーフにした献上柄などがあります。

羅(ら)
羅とは、経糸(たていと)を左右の経糸とからみあわせて織る絹織物の技法です。似た技法である紗(しゃ)は隣り合う2本の経糸を捩る(もじる)のに対し、羅は隣の経糸に絡ませたあと、さらに反対側の経糸にも絡ませるという複雑な構造をもちます。大きな透け感のある織り模様が特徴的です。7世紀ころには中国から伝わり、奈良時代から平安時代前期にかけて盛んに製作されました。
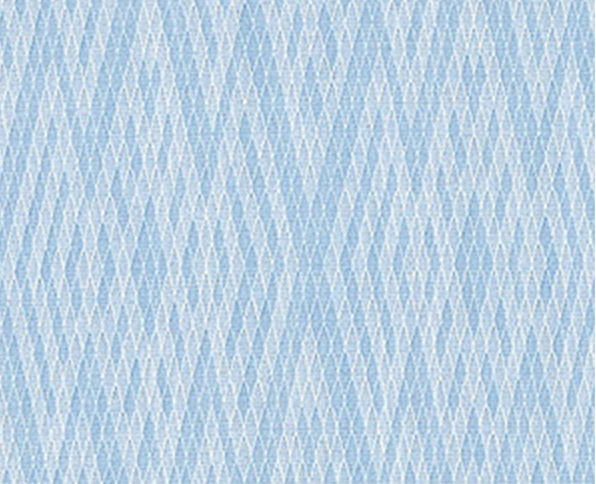
紋紗(もんしゃ)
紋紗とは、平織りと透け感の出る紗(しゃ)織りとで文様を織り出す技法です。紗は綟り(もじり)織りの一種で、隣り合う交差させた2本の経糸(たていと)に緯糸(よこいと)を通して、経糸2本を、緯糸1本ごとに左右に交差させて織るため、織り目に透き目ができ薄くて軽くなります。

風通織(ふうつうおり)
織物の表裏にそれぞれ異なる経糸(たていと)を使って二重組織にする二重織の技法。二重組織となっているため表裏の文様が反対の配色になります。二重になっている中を風が通るという意味から風通という名前が付けられました。

久留米絣(くるめがすり)
久留米絣とは、福岡県久留米市を中心に周辺地域でつくられる織物です。文様を図案化し、織った際にその図案の通りに文様が出るよう、糸を束ねて括った絣括り(かすりくくり)を染色します。括られた箇所は染まらずに白く残り、その糸を使って織ることで特徴的な絣文様を織り出す技法です。この技法自体が、国の重要無形文化財に指定されています。

染織の作家一覧
主な産地
西陣織 Open in new window
西陣織は、京都府京都市北西部を中心に作られている絹織物です。その特徴は、あらかじめ染められた糸を用いる先染めの技法にあり、高級感と、奥深さを感じられます。
加賀友禅 Open in new window
加賀友禅は、石川県金沢市を中心に作られている染色品です。その特徴は、京友禅よりも深みのある落ち着いた色彩と、写実的な草花を中心とした模様にあります。
久留米絣 Open in new window
久留米絣は、福岡県久留米市を中心に周辺地域で作られている綿織物です。手作業で織られた柄のかすれやにじみが特徴です。備後絣、伊予絣と並び日本三大絣の一つに数えられています。
小千谷縮 Open in new window
小千谷縮は、新潟県小千谷市周辺で作られている麻織物です。撚りの強い糸を使うことでできるシボと呼ばれるしわが特徴で、高温多湿の日本の気候に合うさらっとした夏に最適な着物を作り出すことができます。
